WWL・SGHネットワーク令和7年度連絡協議会を開催しました
WWL・SGHネットワーク令和7年度連絡協議会 開催報告
- 開催日 : 令和7年7月23日(水)10:00〜16:30
- 会場 : 文部科学省 東館3階 講堂
- 主催 : 文部科学省
- 共催 : WWLコンソーシアム事務局(株式会社Aoba-BBT)
1. 開催趣旨・概要
WWL・SGHネットワークにおける実践・研究成果の共有と、今後の探究学習の在り方について議論・協議するため連絡協議会が開催されました。WWL拠点校・共同実施校・連携校、SGHネットワーク参加校、高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)の重点類型グローバル型採択校などから95名が参加、探究的な学びやグローバル人材育成、ICT活用の最新事例が紹介され、現場の課題と今後の展望について活発な意見交換が行われました。
2. 開会挨拶
●開会の挨拶
- 登壇者:文部科学省 初等中等教育局 高等学校担当 参事官 橋田 裕 様

令和7年2月に公表された「高等学校教育の在り方ワーキンググループ」の審議のまとめでは、「これからの高等学校の在り方に係る基本的な考え方」として、3つの論点が整理されました。その一つである「社会に開かれた教育課程、探究・文理横断・実践的な学びの推進」を踏まえ、世界で活躍できるイノベーティブな人材の育成に向けて、教育の成果・課題・解決策の共有や、コンソーシアムの構築に積極的に取り組むことへの期待が述べられました。
●事務局挨拶
- 登壇者:株式会社Aoba-BBT 代表取締役社長 柴田 巌

未来を担う若者が、地球規模で課題を捉え、異なる言語・文化・宗教・価値観・国籍をもつ同世代と協働しながら解決に取り組む社会の実現を目指す。そのようなビジョンのもと、先進的な取り組みを進める学校の事例共有やディスカッションを通じて、対話を深めていきたいとの意向が示されました。
あわせて、協議会当日だけでなく、今後も継続的に対話を促進できるよう、オンライン上にプラットフォーム「AirCampus®」を設けたことが説明されました。
3. WWL取組等発表
【取り組み発表① 筑波大学付属坂戸高等学校】共に学び、共に創る未来〜ASEANとの協働から拓くグローバル探究と卒業後へのインパクト〜

WWL(グローバル人材育成強化事業)構想のなかで中心的に進められている海外研修の開発、海外連携校と実施する国際協働探究とユース会議、SGH・WWLで海外研修を経験した卒業生のその後について報告がありました。会場からは、大学との単位互換(先取り履修制度)や海外連携校との共同研究を進める際の研究テーマのマッチングについて質問がありました。
【取り組み発表② 宮崎県立宮崎大宮高等学校】グローバル・イノベーター育成のカリキュラムの開発研究-新教科の構築とグローバルプログラムの相互作用を通して-

WWL事業で育成する人物像を、“枠組みをこえて、多様な人々と協働しながら、創造的な解決方法を提案する力(協創力)をそなえる”「グローバル・コ=クリエイター」と定義、カリキュラムと海外研修の相互作用によって育んでいく取り組みについて発表がありました。
成果として、チームにおける個人の主体性や貢献度の多面的評価、探究の学力測定、探究スキルの変化の分析等に関する手法の開発が進められていると伝えられました。また、このようなプログラムに参加した生徒としなかった生徒では、その後の英語4技能試験の伸びに明らかな差が生じると報告がありました。
【取り組み発表③ 広島大学】グローバルな視点をもつ資質・能力育成のための取り組み:広島大学WWLコンソーシアム構築支援事業


西日本におけるAL(Advanced Learning)ネットワークの中心機関として拠点機関ネットワークの構築や情報の集約、成果の発信を担う立場から、異文化間学習・国際理解学習に関するオンラインセミナーや、地球規模の課題をテーマとしたフォーラムの実施状況を中心に発表がありました。
その中で、各学校のテスト期間や時間割、講師を務める大学教員の空き時間を調整しながら日程や時間を決めることの難しさ、さらに、限られた時間内でグループ討議に十分な時間を確保することの難しさといった課題も確認されました。
4. 専門家セミナー
- 登壇者: 東京大学 総長 藤井 輝夫 氏

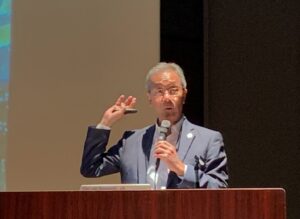
大学の社会的使命と未来の教育のあり方についてお話いただきました。地球規模の課題に直面する中で、大学は対話を通じて新たな知を創出し、社会と連携して課題解決に取り組む場であるべきと強調。市民参加型の海洋観測プロジェクトや、STEAM教育における創造性とアートの重要性にも言及がありました。また、多様性推進の一環として、女性教員や学生の比率向上を目指す取り組み、企業との連携によるキャリア支援の必要性を紹介。さらに、グローバルな学びの場を提供するための英語講義の拡充、新設される「UTokyo College of Design」の構想も発表。学生が自ら問いを立て、社会に変革をもたらす「チェンジメーカー」として成長できる教育環境の整備を目指す姿勢が示されました。
5. グループ別協議

約10名ずつに分かれたグループ別協議を50分×2回行いました。前半の第1部では「グローバル人材育成」を、後半の第2部では「ICT機器等を活用した探究的・文理横断的・実践的な学び」をテーマに取り上げました。どのグループも非常に活発な意見交換がなされ、互いの事例や課題を共有し議論を深める有意義な時間となりました。
6. 全体発表・質疑応答

グループ別協議の後、各グループ代表による全体発表とそれに対する質疑応答が行われました。各グループで深められた内容が共有されるとともに、共通論点の掘り下げや、今後の全国的な連携・制度設計に向け、率直な意見が交わされました。
グローバル人材育成については、「海外研修の費用(円安の影響)」「教員の旅費」「研修で得た学びの継続性」「組織的な取り組みの欠如」が共通の課題として挙げられ、資金調達方法や研修内容を活かす学習機会の提供が議論されました。
ICT活用に関しては、「生成AIの利用」「情報セキュリティ」「教師と生徒のリテラシー格差」が主な論点となりました。AIを単なる答えの検索ツールとしてではなく、対話や創造性の促進にどう活用するかが模索されています。全体を通して、予算の制約と持続可能な教育体制の構築が繰り返し議論されました。
7. 閉会挨拶
- 登壇者:WWL企画評価会議座長 萱島 信子 様 (JICA 緒方貞子平和開発研究所)

グローバル化の進展とともに分断が深まる現代において、SGH・WWL事業の重要性が増していることが指摘されました。パンデミックや国際紛争、自国中心主義の台頭を受け、若者が情報を見極め、国境を越えた発想で社会に貢献し、分断を乗り越える力を育むことが本事業の核心であること、また、教育現場で尽力する教員への感謝と得られた知見やネットワークを活かした教育の発展への期待が語られました。
8. 全体のまとめ
今回の協議会では、物価高や円安の影響で国際交流のコストが上昇し、教員の方々が様々な制約の中で工夫を重ねている様子が印象的でした。共有された知見やつながりが各校に持ち帰られ、今後の実践に良い変化をもたらしていくことを願っています。
《今後のご案内》
- 連絡協議会のアーカイブ動画は、後日、遠隔教育プラットフォーム「AirCampus®」に掲載いたします
- 「AirCampus®」では、他グループの投稿内容もご覧いただけますので、他校の取り組みに触れていただく機会としてぜひご活用ください
- あわせて、すべての参加者が意見交換できるディスカッションフォーラムも開設予定です。引き続き、テーマごとの交流を深めていただければ幸いです
- 「AirCampus®」のログインや操作に関してご不明な点がございましたら、お気軽にWWLコンソーシアム事務局〈 wwl@ohmae.ac.jp 〉までお問い合わせください
9. 付録
- グループ協議記録用紙:【連絡協議会】グループ別協議:ディスカッションシート.pdf
- 当日プログラム:【事務連絡】連絡協議会の当日プログラム(株式会社Aoba-BBT発信).pdf

